マテリアルデザインとは?活用するメリット・デメリット、制作での重要ポイントを解説
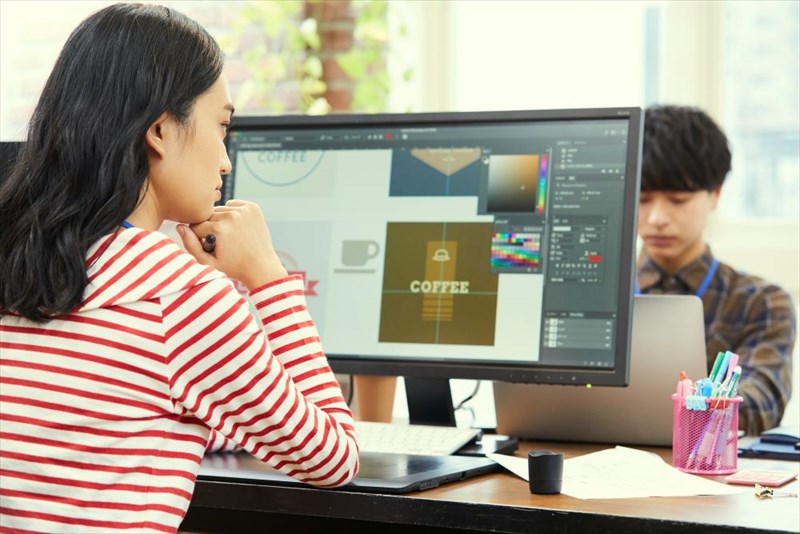
マテリアルデザインとは、Google社が推奨するデザインであり、ユーザーが見やすく扱いやすいホームページを作成するのに役立ちます。しかし、具体的にどのようなデザインなのか、どうすればマテリアルデザインを意識した見やすいホームページを構築できるのか知りたい人もいるでしょう。
本記事では、マテリアルデザインとは何か、メリットとデメリット、マテリアルデザインを活用する際の重要なポイントなどについて解説します。
マテリアルデザインとは?
マテリアルデザインとは、Googleが2014年に発表した新しいデザインのガイドラインです。
マテリアルデザインとは、「物質的な」「具体的な」デザインという意味です。ユーザーが直感的に理解して、操作できるデザインのコンテンツを構築するためのガイドラインとして発表されました。
一般的なホームページなどは操作性や見た目がさまざまですが、ページごとに毎回情報を読み取り操作方法を覚えるのは不便です。しかし、マテリアルデザインを取り入れたホームページは、画面を見れば誰でも直感的に操作方法がわかるようになっています。
誰でも操作しやすく見やすいホームページを構築できれば利用者が増えるので、ホームページを制作するなら押さえておくと良いでしょう。
フラットデザインとの違い
マテリアルデザインとよく似た用語にフラットデザインという用語がありますが、何が違うのでしょうか?
フラットデザインとは平面的でシンプルなデザインであり、画面上の変化がなく過剰な装飾などを行いません。無駄をそぎ落とした平面的なデザインなので、ファイル容量を抑えられるメリットがあります。
一方、マテリアルデザインはシンプルデザインとは異なり、アニメーションなども多用してユーザーが視覚的にわかりやすいデザインです。
マテリアルデザインのメリット
次に、マテリアルデザインを取り入れるメリットについて解説しましょう。
ユーザーが直感的に操作できる

マテリアルデザインのもっとも大きなメリットは、ユーザーが直感的に操作できる点です。
「インク要素」を活用すれば、コンテンツに合わせて効果的な色使いや配置、アニメーションなどを組み合わせられます。その結果、現実世界に近い状態を表現できるので、イメージがわきやすくユーザーは操作しやすくなるのです。
そのため、初めて操作するユーザーでも画面を見て直感的に操作できます。
スキルがなくても質の高いコンテンツを制作できる
マテリアルデザインについては、Googleの公式サイトに必要な情報がそろっています。そのため、情報を手に入れやすく、それらの情報を参考にすればスキルがなくても質の高いコンテンツを制作できます。
マテリアルデザインに関する概要や基本知識、詳しいデザイン方法などの情報が豊富なので、誰でも学べます。それらの情報をもとにデザインすれば、時間をかけて勉強しなくても、ある程度のクオリティのコンテンツを制作できるでしょう。
ルールを覚えれば短時間で制作できる
マテリアルデザインに関する情報は、Googleの公式サイトで簡単に入手できます。
Googleが推奨するマテリアルデザインのルールは、メインカラーを1色に決める、サブカラーはメインカラーと同系色など、詳しく定められています。それらのルールどおりに制作していけば、誰でも短時間で質の高いホームページを制作できるようになるでしょう。
マテリアルデザインのデメリット

マテリアルデザインには上記のとおり多くのメリットがありますが、一方でデメリットもあります。ここでは、マテリアルデザインのデメリットについてご説明しましょう。
デザインの差別化が難しい
マテリアルデザインはルールが決まっているため、そのとおりにコンテンツを制作すれば良いメリットがあります。しかしその反面、どれも似たようなデザインになりがちで、デザインの差別化が難しいデメリットもあるのです。
使える色の種類やパターンが限られているなどの制約から、他のコンテンツと差別化を行うのが難しいです。そのため、マテリアルデザインのルールを守りつつ、独自性のあるデザインを作る工夫が必要になるでしょう。
ページの読み込みに時間がかかる
マテリアルデザインを取り入れたホームページは、アニメーションや動きのある画像、アイコンなどを多用するケースが多いため、容量が大きくなりがちです。そのため、ページの読み込みに時間がかかるデメリットがあります。
読み込みが遅いページはユーザーが離脱する可能性が高いので、画像の容量を軽くするなどして読み込み時間を速くする工夫が必要です。
マテリアルデザインを活用する際に重要なポイント

マテリアルデザインを活用する際に、気をつけたい重要なポイントについてご説明します。
ボタンに厚みを出すなど物理的法則を取り入れる
画面に配置するボタンに厚みを出す、立体的なものには影をつけるなど、現実世界における物理的な法則をホームページに取り入れます。ボタンに厚みがある表現を取り入れれば、ユーザーがそれをボタンだと認識しやすくなり自然にボタンを押す動作につながります。
このように、画面に現実世界と同じ物理法則を取り入れれば、ユーザーは直感的に「ボタンを押す」動作ができるようになります。
印刷物の「紙」と「インク」と同じルールで組み立てる
マテリアルデザインで重要なのは、「紙要素」と「インク要素」です。
現実世界にある「紙」をイメージして、厚みや色、自由に伸縮できる素材感などを意識します。画面上にボタンやバー、リストなどを置く場合は、紙で構成するイメージで設置します。
紙に文字や写真、動画などを設置する場合は、インク要素として表します。実際に紙にインクを乗せるようにイメージして、ユーザーが見やすく操作しやすいデザインを作っていく点が重要です。
色の数を限定したうえで配色する
マテリアルデザインで使える色の数は、以下のように決められています。
有彩色は4色で、ホームページ全体のメインカラーが1色、メインカラーと同系色が2色、目立たせたい要素に使用する色が1色です。それ以外に黒やグレー、白などの無彩色も使用できます。
このように使用できる色の数などのルールを守って、コンテンツを制作する必要があります。
影を活用する
コンテンツには自然な陰影をつけます。
例えば、ボタンに影をつけて厚みを表現すれば、ユーザーは直感的にボタンであることを認識でき、自然とボタンを押せます。また、画面上の区切りに影をつけておけば、その区切りが境になっていることが表現されるようになります。
このように自然な陰影があると、コンテンツの内容が視覚的にわかりやすくなるため、ユーザーが認識しやすくなります。
連続性のあるアニメーションを取り入れる
ユーザーの動きに合わせて連続性のあるアニメーションを取り入れれば、ユーザーの操作を補助できる効果がでてきます。
例えば、ボタンを押した時に何も反応がないと、ユーザーはボタンを押せたかどうかを判別できず、何度も押してしまうことがあります。そこで、ボタンを押すとカチッという音を出す、押した動作に合わせてボタンがへこむなどの動きを取り入れます。そうすれば、ユーザーはちゃんとボタンを押せたことを認識できるでしょう。
まとめ
本記事では、マテリアルデザインとは何か、メリットとデメリット、マテリアルデザインを活用する際の重要なポイントについて解説しました。マテリアルデザインを取り入れれば、ユーザーに予備知識がなくてもわかりやすく操作しやすいホームページを制作できます。
しかし、マテリアルデザインを取り入れたホームページ制作は自分ではなかなか難しい場合もあると思います。そのような時は、豊富なノウハウを持つ株式会社プラストをぜひご利用ください。

